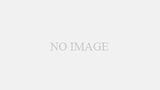■ハルヒ問題とは?オタク発の難問が数学界を揺るがす!
皆さん、こんにちは!ネットの話題にアンテナを張り巡らせている30代前半ブロガーの独身男です。最近、ネット界隈でなにやら面白いワードを見かけましてね。「ハルヒ問題」…一体なんだこれは?と、いつものように深掘りしてみました。
ハルヒ問題、それは数学界のガチ問題だった!
「ハルヒ問題」と聞いて、アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』を連想した方は多いはず。僕も最初は、「また何かオタク界隈のネタか?」くらいに思っていました。ところがどっこい、調べてみるとこれはマジモンの数学の問題だったんです!
事の発端は2011年。匿名掲示板4chanの数学板に、ある匿名の人物が「涼宮ハルヒの憂鬱」のテレビアニメ第一期全14話を、考えられる全ての放送順で連続して視聴する場合、最低限必要な視聴回数は何回になるのか?という問いを立てたことに始まります。
アニメの放送順は、時系列順ではなかったため、ファンたちの間で「どの順番で見るのが一番効率的なのか?」という議論が交わされていたんですね。この素朴な疑問が、実は数学の難問「最小超置換問題」と深く関わっていたというから驚きです。
「ハルヒ問題」の最小超置換問題とは?
では、「最小超置換問題」とは一体何なのでしょうか?簡単に言うと、「n個の異なる記号の全ての順列(並べ方)を、部分文字列として含む最も短い文字列の長さを求める」という問題です。
例えば、A、B、Cの3つの記号があったとします。この3つの記号の順列は全部で3!(3の階乗)=6通りありますよね(ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA)。これらの全ての順列を部分文字列として含む最も短い文字列は「ABCABACBA」で、その長さは9になります。
「ハルヒ問題」は、この最小超置換問題において、n=14(ハルヒアニメの全14話)の場合に、最小の文字列の長さを求めることに相当するわけです。
「ハルヒ問題」はオタクの疑問が数学者を動かした!?
この4chanでの匿名の提起は、当初こそ一部のネット民の興味を引くに過ぎませんでしたが、2018年になって数学者でコンピュータ科学者のロビン・ヒューストン氏がこの問題に注目し、Twitterで言及したことで、一気に数学界隈でも話題になったんです。
さらに驚くべきことに、ヒューストン氏らは、この匿名の4chan投稿者(Anonymous 4chan Poster)を筆頭著者として、より洗練された証明を発表しました。まさか、アニメ好きの何気ない疑問が、長年未解決だった数学の難問に光を当てることになるとは…まさに「オタクの情熱、恐るべし!」ですよね。
ハルヒ問題の現在地と個人的な感想
現在、「ハルヒ問題」を含む最小超置換問題は、まだ完全に解決には至っていません。しかし、2018年には、下限と上限を示す研究が進展し、n=14の場合、全てのエピソードを全順序で視聴するには、少なくとも約938億話以上、多くとも約939億話程度が必要であることが示唆されています。
…939億話って!想像を絶する数字ですよね。仮に1話24分だとしても、一生かかっても見終わらない計算になります。
個人的な感想としては、この「ハルヒ問題」が、単なるアニメの視聴順というオタク的な話題から、数学の未解決問題に発展したという経緯が、めちゃくちゃ面白いと感じています。アニメというポップカルチャーが、まさかアカデミックな分野に影響を与えるなんて、なんだか夢がありますよね。
そして、この問題を提起した匿名の人物が、まさかの論文の筆頭著者になっているというのも、ネットならではの面白い現象だと思います。もしかしたら、僕たちが普段何気なくネットで発信する言葉の中にも、未来の誰かの研究テーマになるような、とんでもないポテンシャルが秘められているのかもしれません。
これからも、このような予想外なネットの話題を追いかけて、皆さんと一緒にワクワクしていきたいですね!それでは、また次の話題でお会いしましょう!